古本市が好きで機会があればあちこち行ってることは、何度か書いたことがあります。中でも京都の下鴨神社でお盆に開催される「納涼古本まつり」はよく行くんですけど一昨年コロナで中止、昨年は都合つかずで今回3年ぶりに行ってきました。
 神社の広い境内で、左右には森が広がっており上空は張り出した巨木の枝葉が日陰を作っています。森の湿った香りとテントの会計レジで焚いてる蚊取り線香の香りと、膨大な古書が発する香りが入り交じり独特の匂いが満ちています。いつもこの香りを嗅ぐと、夏が終わっていくなあと感じます。小学生時代、地蔵盆のお祭りが過ぎると夏休みの終わりをいやでも実感しこの世の終わりのような暗澹たる気分になりました。あのときの空気感を思い出します。
神社の広い境内で、左右には森が広がっており上空は張り出した巨木の枝葉が日陰を作っています。森の湿った香りとテントの会計レジで焚いてる蚊取り線香の香りと、膨大な古書が発する香りが入り交じり独特の匂いが満ちています。いつもこの香りを嗅ぐと、夏が終わっていくなあと感じます。小学生時代、地蔵盆のお祭りが過ぎると夏休みの終わりをいやでも実感しこの世の終わりのような暗澹たる気分になりました。あのときの空気感を思い出します。
広い会場内を2時間ちかくぶらぶらしたでしょうか。目ぼしい掘り出し物も見つからず、この日は島崎藤村の「若菜集」の初版本だけを買って帰りました。家から往復2時間かけて古書1冊、買い物の成果だけみるとなんとも非効率的ではありますが、気分的には有効な時間の使い方でした。
古書・古本業界は、作家や出版関係者にとってはあまり喜ばしい存在ではありません。古本は、客が買っても出版社や作者には1円も入らないからです。理不尽な気もしますが、書籍などの著作物(映画DVDを除く)はいったん適法に販売された時点で著作権者の譲渡権が及ばなくなるので、買った人はそれを誰かに売ろうが自由なのです。だから古本屋さんの商売が成り立つのです。
これは消費者にとってもありがたい。書籍やCDなんかは本来、独占禁止法の規制の例外とされてて、再販制度により新刊書は日本中どこでも同じ値段です。今週号の少年ジャンプを1円でも安い店を探して買うなんてことはできません。

ところが譲渡権が無くなった古書はパソコンや豚コマ肉と同じで、お店はいくらで売ろうと自由になります。ボロボロの漫画本に1冊数千円から数万円のプレミア価格がついたり、人気がない文庫や新書なんかは新品同様でも1冊100円でワゴンに並べられるのです。
わたしもよく古本買います。新刊のベストセラーやなんかは古本屋さんになかなか出てこないのでamazonやリアル本屋さんで求めますが、何かの拍子に興味がわいた本はたいてい中古を買います。安い。しかも本から得られる情報の質・量は新品と同じで、これが他の中古物品との大きな違いです。
先日、そんな古本屋さんを舞台にした「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ、たまたま読み始めたらはまってしもて、とうとう全部読んでしまいました。いちおうミステリーなのですが、ラノベというカテゴリに入るのでしょうか、軽い文章なんで1日の通勤往復で1冊のペースで読めました。
映画化ドラマ化もされた作品なんで「小説とはいえいくらなんでもそれは無いでしょう」的な展開はまあ、マンガ読んでると思えば納得できます。それより、作者は古書店に勤務したことがあるとかで、業界の内側が垣間見られたところがなかなかに面白かったです。全部amazonで中古を買いました。当然ですが、内容は新刊本と変わりません。この得した気分は、なかなかに小さな幸せなのです。

 マ
マ
 江戸時代、はずみで主人を殺して逃げた侍が、逃げた先々でもやけになって悪事を重ねたのちに改心して出家の旅に出ます。九州豊前の国の海岸崖沿いにある通行の難所に至り、自分の罪滅ぼしとしてここに安全に通れる道を通そうと堅い岩山に金づちとのみで一人トンネルを掘り始めます。当初土地の住民からはバカにされますが、その後理解を得て手伝ってもらうものの、すぐにまた一人になってという作業を延々続けるうちに20年以上が経過します。一方、殺された主君の子もまた仇を求めて全国を経巡るうちとうとうこのトンネル堀りの現場で仇敵を発見します。すぐに殺そうとしますが、完成するまで待ってやれという沿線住民の要請もありいったん延期して、早く開通させるため自分も一緒に穴掘りを手伝う羽目になります。ようやく貫通したとき坊さんに「約束やし、さあ斬れ」と言われても、「敵を討つなどという心よりも、このかよわい人間の双の腕かいなによって成し遂げられた偉業に対する驚異と感激の心とで、胸がいっぱい」になって、とても復讐など実行できませんでした、というお話です。
江戸時代、はずみで主人を殺して逃げた侍が、逃げた先々でもやけになって悪事を重ねたのちに改心して出家の旅に出ます。九州豊前の国の海岸崖沿いにある通行の難所に至り、自分の罪滅ぼしとしてここに安全に通れる道を通そうと堅い岩山に金づちとのみで一人トンネルを掘り始めます。当初土地の住民からはバカにされますが、その後理解を得て手伝ってもらうものの、すぐにまた一人になってという作業を延々続けるうちに20年以上が経過します。一方、殺された主君の子もまた仇を求めて全国を経巡るうちとうとうこのトンネル堀りの現場で仇敵を発見します。すぐに殺そうとしますが、完成するまで待ってやれという沿線住民の要請もありいったん延期して、早く開通させるため自分も一緒に穴掘りを手伝う羽目になります。ようやく貫通したとき坊さんに「約束やし、さあ斬れ」と言われても、「敵を討つなどという心よりも、このかよわい人間の双の腕かいなによって成し遂げられた偉業に対する驚異と感激の心とで、胸がいっぱい」になって、とても復讐など実行できませんでした、というお話です。 この話のもとになったトンネルは「青の洞門」といって大分県中津市に実在し、指定文化財、観光名所になってます。実際は偉い坊さんが托鉢で資金を集めて作ったといいますから、小説は菊池寛の創作とは言え史実にインスピレーションを得たのでしょう。ちなみに開通後は通行料を取ってたので、日本最古の有料道路とも言われてるそうです。
この話のもとになったトンネルは「青の洞門」といって大分県中津市に実在し、指定文化財、観光名所になってます。実際は偉い坊さんが托鉢で資金を集めて作ったといいますから、小説は菊池寛の創作とは言え史実にインスピレーションを得たのでしょう。ちなみに開通後は通行料を取ってたので、日本最古の有料道路とも言われてるそうです。
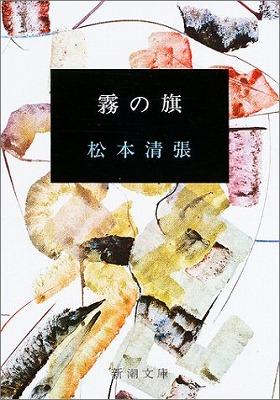 これまで読んだり観たりした復讐劇のうち、このパターンに当てはまらないものがひとつだけありました。それがかの松本清張の小説「霧の旗」です。有名な作品で、繰り返し映画・ドラマ化されてるんで「ああ」と思われる方も多いでしょう。ネタバレで続けます。
これまで読んだり観たりした復讐劇のうち、このパターンに当てはまらないものがひとつだけありました。それがかの松本清張の小説「霧の旗」です。有名な作品で、繰り返し映画・ドラマ化されてるんで「ああ」と思われる方も多いでしょう。ネタバレで続けます。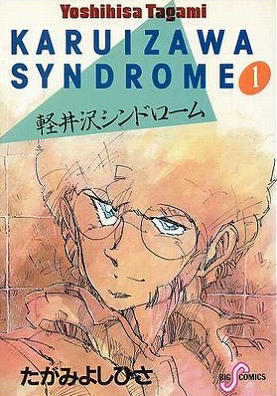 作者たがみよしひさ氏は
作者たがみよしひさ氏は